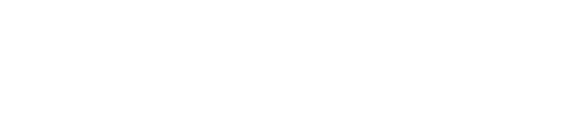法人向け自動車保険
法人向け自動車保険お役立ち情報
検知器によるアルコールチェックが義務化!
企業に必要な対応は?
更新日:2025年1月21日
公開日:2024年5月15日

これまで緑ナンバー車のみに義務づけられていたアルコール検知器による酒気帯び確認が、2023年12月から白ナンバー車にも義務化されるようになりました。どのような企業がこの義務化の対象になり、該当する場合は何をしなければならないのでしょうか。白ナンバー車のアルコールチェック義務化に関する法改正の概要や企業に必要な対応について解説します。
アルコールチェックの義務化
アルコールチェックの義務化は、従来はバスやトラック、タクシーなどのいわゆる緑ナンバーの事業用自動車を対象としていました。緑ナンバー車とは、貨物や人を有償で運ぶことを目的としている自動車のことで、貨物運送業や旅客運送業といった特定の事業を行う法人・個人事業主で使用されています。
一方、白ナンバー車は事業の一環として使用する自動車を指し、無償で自社の荷物や人を運ぶ点が主な違いです。道路交通法の改正により、これまで義務の対象外であった白ナンバー車も、一定の条件を満たす場合はアルコールチェックが義務づけられ、段階的な施行が進められました。
2022年4月から施行の改正内容
- 運転前・後の2回にわたるアルコールチェックを目視などで行うこと
- 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保管すること
2022年4月から施行された改正では、アルコール検知器による数値での確認までは義務づけられておらず、目視などの手段でよいとされていました。背景には、検知器の導入コストや準備期間を設ける必要があったことが影響しています。また、アルコールチェックを運転前だけでなく運転後にも行うのは、運転中の飲酒を防止するためです。
2023年12月から施行の改正内容
- アルコール検知器を使用した酒気帯び確認を行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持(*)すること
2023年12月からは、すでに施行済みの「目視による酒気帯び確認」と「確認結果の記録と保管」に加え、アルコール検知器の導入が義務化されました。同時に、機器の故障や動作不良などがあると、適切なチェックが行えず、事故や法令違反のリスクが高まるため、アルコール検知器の定期的な点検と、常に正確な測定ができる状態の維持も必要となります。
また、アルコール検知器は各営業所に常備するとともに、遠隔地での業務や移動中のチェックが必要な際は、携帯型アルコール検知器を持参して対応することも求められます。
「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持すること。
アルコールチェック義務化の対象が拡大された背景
アルコールチェック義務化が進んだのは、2021年6月に千葉県八街市で下校途中の小学生5名が飲酒運転をしていたトラックにはねられて死傷した事故がきっかけです。事故を起こしたトラックは白ナンバー車で、当時アルコールチェックが義務化されていなかったため、事故の際も実施されていませんでした。この事故をきっかけに、警視庁は安全対策を強化することになり、道路交通法施行規則が改正され、緑ナンバー車と同様、白ナンバー車の運転者に対するアルコールチェックが義務化されるようになりました。
アルコールチェック義務化の対象となる企業
アルコールチェック義務化は、次のいずれかの条件を満たす場合に適用されます。
- 乗車定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上保有している場合
- 白ナンバー車5台以上を保有している場合
これらの条件を満たす事業所は「安全運転管理者選任事業所」と呼ばれ、安全運転管理者の選任とアルコールチェック義務化の対象です。事業所とは、対象となる車が業務で使用される拠点(営業所や事務所など)を指すため、拠点が複数ある場合は場所ごとに業務で使用する車の台数を計算します。
台数の算定方法に注意
事業所で使用する車の台数を算定する際、どの車が対象に含まれるのか迷う場合があります。次のポイントを押さえ、正しい台数を把握しましょう。
二輪車を業務に使用している場合
自動二輪車は「1台 = 0.5台」で計算します。ただし、原動機付自転車は算定に含みません。
マイカー通勤を許可している場合
通勤は業務ではないため、通勤のみに使用する場合は算定に含みません。ただし、通勤と業務の両方で使用する場合は算定に含みます。
所有者が企業ではない車がある場合
従業員が所有している車やリース車であっても、業務で使用する場合は算定に含みます。
アルコールチェックは安全運転管理者の業務
アルコールチェックの実施は、法律上、安全運転管理者の業務です。法改正により条件を満たす白ナンバー車にもアルコールチェックが義務化されたことで、安全運転管理者の業務に「酒気帯びの有無の確認と記録・保管」と「アルコール検知器の常時有効保持」が追加されました。
そのため、白ナンバー車が一定の条件に該当した場合は、安全運転管理者を選任した上で、安全運転管理者にアルコールチェックを実施させなければなりません。また、事業所が保有する車の台数によっては、安全運転管理者の業務を補助する「副安全運転管理者」の選任も必要となります。具体的な台数と人数の基準は次のとおりです。
| 1台~19台 | 不要 |
| 20台~39台 | 1人 |
| 40台~59台 | 2人 |
| 以降20台ごとに1人追加で選任 | |
対象企業が行うべき対応
新たにアルコールチェック義務化の対象となる企業・事業所は、どのような対応が必要になるのでしょうか。白ナンバー車を使用する企業に求められる4つの対応を解説します。
安全運転管理者の選任
一定の条件に該当した場合は、安全運転管理者を選任し、15日以内に事業所を管轄する警察署へ届け出なければなりません。安全運転管理者は、従業員(運転者)の安全運転を確保するために必要な業務を行う担当者として、アルコールチェックのほか、運行計画の作成、安全運転教育などの業務を担います。
事業所で使用する車の台数を算定する際、どの車が対象に含まれるのか迷う場合があります。次のポイントを押さえ、正しい台数を把握しましょう。
安全運転管理者について詳しくは安全運転管理者とは?選任方法や業務内容、罰則について解説をご覧ください。
アルコール検知器(アルコールチェッカー)の配備
アルコール検知器は特段性能上の決まりはなく、呼気中のアルコールを検知し、飲酒の有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値などにより示す機能を有する機器であれば問題ありません。直行直帰がある場合は、事業所に備えつける検知器以外に携帯型の検知器も用意しましょう。
チェックの記録および保管
アルコールチェックの結果は記録のうえ、1年間保管することが義務づけられています。
具体的な記録項目は以下のとおりです。
- 確認者名(安全運転管理者)
- 運転者名
- 自動車のナンバー(運転者の業務にかかる自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など)
- 確認の日時
- 確認の方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- そのほか必要な事項
指定の記録簿様式はないため、独自に用意したフォーマットで作成が可能です。また、作成した書類の保管方法は紙・データのどちらでも可能です。
従業員の意識徹底
アルコールチェックの実施にあたっては、安全運転管理者だけでなく、全従業員が実施背景や運用ルールを把握することが大切です。アルコールチェックの実施体制や運用ルールを整備したうえで、事業所内に周知しましょう。また、飲酒運転の危険性やアルコールチェックの重要性などを理解させるために社内研修を実施して、全従業員に安全運転の意識付けをしていく必要があります。
アルコールチェック義務を怠った場合の罰則
アルコールチェックは運転者の安全を確保し、飲酒運転を未然に防ぐための重要な義務です。そのため、アルコールチェックを適切に実施しない場合は、法律にもとづく処分が行われます。
安全運転管理者の義務違反
現時点では、安全運転管理者がアルコールチェックを怠った場合の直接的な罰則は定められていません。ただし、安全運転管理者の義務違反に該当するため、公安委員会から安全運転管理者の解任命令を受ける可能性があります。
また、企業・事業所が安全運転管理者に対し、業務を行うのに必要な権限や機材などを与えていない場合は、企業・事業所も是正措置命令の対象です。解任命令や是正措置命令に従わないときは、50万円以下の罰金が科せられることもあります(道路交通法第119条の2)。
飲酒運転に該当した場合は厳しい罰則が科せられる
アルコールチェックを怠ると、運転者が飲酒した状態で運転してしまうリスクが高まります。万一、飲酒運転が発覚した場合、運転者本人だけでなく、使用者である企業・事業所や同乗者なども罰則の対象です。
それぞれの罰則は、運転者が「酒気帯び運転」の場合と「酒酔い運転」の場合で異なります。酒気帯び運転は呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上、酒酔い運転はアルコールの影響により、車の正常な運転ができないおそれがある状態を指し、酒気帯び運転よりも悪質と判断されます。
運転者
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金+免許停止または免許取り消し(アルコール濃度と累積点数による)
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金+免許取り消し
車の提供者
飲酒を認識していながら従業員に運転をさせた場合に、企業・事業所の代表者、責任者に科せられる罰則です。
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
同乗者・酒類の提供者
飲酒を認識していながら同乗していた人や、運転することを知っていながら酒類を提供した人に科せられる罰則です。
酒気帯び運転:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒酔い運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
アルコールチェックを実施する際の注意点
アルコールチェックを受ける従業員の対象
アルコールチェックの対象者は、業務で車を運転するすべての従業員です。社用車を運転する従業員だけでなく、レンタカーやマイカーを業務に使用する従業員も、必ずアルコールチェックを受ける必要があります。一方で、通勤のみに車を使用する従業員は、アルコールチェックの対象外です。ただし、飲酒運転を防止するための社員教育を実施するなど、企業・事業所としての対策をすることが望ましいでしょう。
安全運転管理者が不在の場合
安全運転管理者が不在でアルコールチェックができない場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する人、業務委託を受けた人が代理でアルコールチェックを実施することが認められています。ただし、安全運転管理者以外の人がアルコールチェックを行い、従業員の酒気帯びを確認した場合は、安全運転管理者に速やかに報告の上、対応の指示を受けなければなりません。
直行直帰の場合のチェック方法
アルコールチェックの確認方法は「対面」が原則です。しかし、直行直帰で対面による確認が難しい場合は、カメラやモニター、携帯電話、業務無線などで運転者の顔色や声の調子を確認するとともに、携帯型アルコール検知器の測定結果を報告させる方法が認められています。この場合、対面による確認と見なせるよう、特に注意して実施しましょう。
行きと帰りで運転者が変わる場合
運転者が途中で交代する場合でも、運転者ごとに運転前・後のアルコールチェックが必要です。行きと帰りで運転者が変わる場合は、行きの運転者は運転前と目的地に着いた後、帰りの運転者は目的地から出発する前と帰社後にアルコールチェックを実施します。その際、目的地でほかの事業所の安全運転管理者がアルコールチェックに立ち会った場合、運転者は所属する事業所の安全運転管理者へ測定結果を電話などで直接報告しなければなりません。
アルコールが検出されたときの対応
運転前のアルコールチェックでアルコールが検出された場合は、その程度にかかわらず運転させることはできません。また、運転前の確認では問題がなくても、運転後にアルコールが検出された場合、運転中に飲酒をした可能性があります。飲酒運転が明らか、または疑われる際は、警察への通報が必要です。なお、アルコールチェック自体を拒否する場合も、運転させることはできません。
安全運転を徹底するためにもアルコールチェックは適切に実施しよう!
2023年12月から白ナンバー事業者にもアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されました。飲酒運転は重大事故に直結する犯罪行為であることはもちろん、企業の社会的信頼を失墜させる要因となるため、義務に反することは大きなリスクとなります。
「飲酒運転をしない、させない」ためには、アルコールチェックだけでなく、安全運転管理者、運転者である従業員、事業者が一丸となり会社全体で安全運転に対する意識を高めていくことが大切です。
監修者 佐藤 寿美礼
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会認定)

監修者 佐藤 寿美礼
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会認定)
2016年からフリーランスとして活動。金融や投資、税金、保険、住宅ローン、不動産、社会保障制度など、「お金」関係の記事を中心に編集や執筆をしています。子どもの大学進学やマイホーム購入などをきっかけに、お金の管理に興味を持ち、投資や保険、法律などを勉強中です。